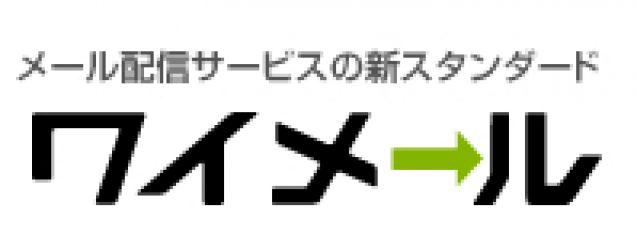今回もワイメール公式コラムをご覧いただき、ありがとうございます。
メールマーケティングを行う中で、自分が送信したメールが迷惑メール(スパム)扱いを受けていないかは多くの担当者について常に関心を持つ事柄です。
中でも近年「Spamhaus Project」という団体によるブロックリストについて耳にしたり、人によっては配信環境のIPアドレスやドメインがリストに追加されたことで、その存在を認識されている方は多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、Spamhausが2025年6月19日に公開した、「Spamhaus’ take on Cold Emailing…AKA spam」というブログ記事を参照し、Spamhausがスパムと定義するメール、中でも「コールドメール」と呼ばれるメールについて確認し、送信者はどのように対応すればよいか考えていきたいと思います。
目次
Spamhausとは
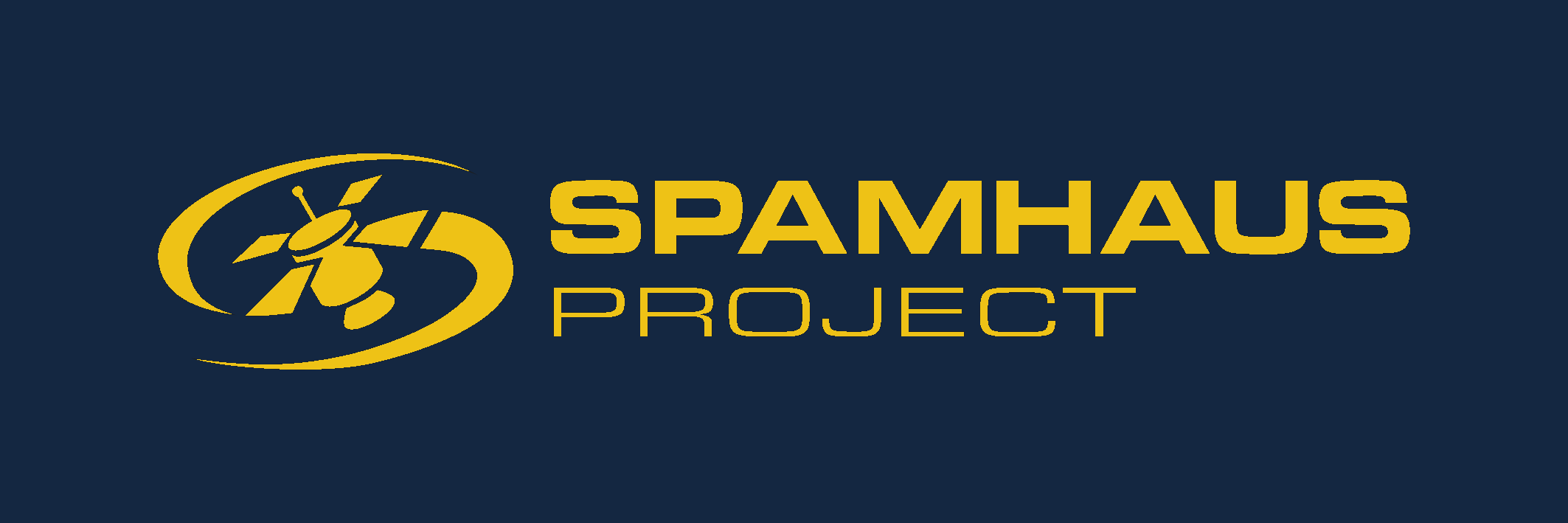
Spamhaus Projectとは、1998年に設立された非営利団体です。
インターネット全体の信頼と安全性を強化するという使命のもと、世界中のスパム、フィッシング、マルウェア、ランサムウェアに関連するIPやドメイン、ASN(ネットワークID)についての情報を収集し、データの提供を行っています。
これらの情報は、スパムフィルターからのレポート、提携するスパム対策サービスやISPからの情報提供のほか、Spamhausが発行した「スパムトラップ」と呼ばれる、囮のメールアドレスに配信されたメールを分析することなどで蓄積されています。
GmailやYahoo! Mail、Microsoft系メール(Outlook, Hotmail, Microsoft 365等)、iCloud Mailなど、日本国内でもよく利用されるフリーメールサービスでもSpamhausが提供するブロックリストをスパム判定や送信元のブロックに活用しているとされます。
Spamhausのブロックリスト登録による影響は大きく、場合によっては登録されただけで受信ブロックが発生することもあります。
今日のメールマーケティングでは、配信環境がSpamhausのリストに登録されていないかどうかは非常に重要な要素であり、実質的な到達率に大きく影響するため無視することはできません。
コールドメールとは
さて、2025年6月19日にSpamhausのチームによって投稿されたブログ、「Spamhausによるコールドメール(いわゆるスパム)に関する考察」(邦訳題)から、「コールドメール」の定義について確認していきましょう。
Spamhaus’ take on Cold Emailing…AKA spam
「コールドメール」とは、電話における「コールドコール」のメール版で、これまでに関係のない相手へ業務的に送る“未承諾のメール”を指します。
ただし、過去につながりのない2者間で、正当な1対1でのメッセージが送信されることは問題ないとされています。
問題は「コールドメール」が自動化され、大規模化し、大量に送信されるようになった際に発生するとされ、この「自動化」「大規模化」が個人的なメッセージからスパムへと変化する要因です。
近年、LinkedInなどのスクレイピング(Webコンテンツを自動収集する行為)などで収集した情報を用いて、多数の受信者に無関係なメールを送信する企業が増加しているとされています。
また、大規模言語モデル(LLM)や人工知能(AI)の発達によってターゲティングの最適化や、スパムフィルタにかからないよう内容のパーソナライズなどが行われており、今後もこの形式のスパムが増加することをSpamhausは懸念しています。
そもそもSpamhausは何をもって「スパム」とするのか
SpamhausはそのFAQで、「スパム」の定義を明確に示しています。
A message is Spam only if it is both Unsolicited and Bulk.
(メッセージがスパムとなるのは、未承諾かつ大量送信である場合のみです。)
「Unsolicited(未承諾)」は受信者がメッセージの送信を検証可能な形で許可していないことを意味し、より平易に言うとあとから取り消しが可能な事前の同意(オプトイン)を得ていない送信です。
「Bulk(大量送信)」は、実質的に同一の内容を持つメッセージの一斉配信を指します。
つまり、相手の名前の挿入や文章表現の差異などでパーソナライズされていても、内容が実質的に同一で、大きなリストに向けて配信されるメールは「Bulk(大量送信)」であるということです。
興味深いのは、「Unsolicited(未承諾)」かつ「Bulk(大量送信)」がスパムの定義であり、それぞれの構成要素はそれ自身ではスパムに該当しない点です。
オプトインを得ていないメールの送信は、初コンタクトの相手との最初のやり取りのように必然的に発生するプロセスであり、同一内容の大量配信は会員宛のメールマガジンなどで通常に行われる行為ですが、これらが組み合わさることで初めてスパムとして判断されます。
スパムは同意の問題である
「only(場合のみ)」とされている通り、送信方法が問題なのであって、送信された内容には関わりがない点にも注意する必要があります。
そのメッセージが詐欺であれ、正当なビジネスメールであれ、内容にかかわらずオプトインを得ずに大量送信されているのであればスパムです。
メッセージの内容に関係がないというのは重要で、通常法律等でスパムメッセージの内容を規制するには判断基準の検討に膨大な時間がかかり、言論の自由などとの兼ね合いが難しい一方、実質的に他の受信者に配信された内容と同一であるか、事前の同意があったかについては定量的に、容易に判断しうるものであるからです。
コールドメールとスパムに違いはない
スパムの定義と問題とされるコールドメールの定義を並べてみましょう。
スパム
- オプトインを得ていない
- 大量の送信である
コールドメール
- これまでに関係のない相手へ業務的に送る“未承諾のメール”
- 1対1ではなく、自動化され、大規模化している
両者に定義上の違いはなく、コールドメールとは、Spamhausがスパムとして扱うメールであることがわかります。
この定義に当てはまるのであれば、送信者自身が正当な「新規開拓の営業メール」であると考えていても、Spamhausからは「コールドメール/スパム」であるとみなされ、ブロックリストへの追加が行われることになります。
コールドメールは本来一律にスパムとしては扱われていなかった
本来のコールドメールは、無差別に送られるものではなく、興味を持ちそうな相手を慎重に選び、正直に意図を伝えながら送られるケースが一般的でした。
そのような場合、正当なビジネス上の関心として一定の理解を得られることもあり、一律にスパムと断定されるものではありませんでした。
もっとも、受信者の視点から見ればコールドメールは「望まれていない連絡」であり、本質的にスパム的な要素を含みます。
そのためSpamhausも、コールドメールを「一定の正当性がある場合もあるが、常にベストプラクティスを守らなければならない」と強調しています。
現在のコールドメールは法律と倫理のグレーゾーン
本来のコールドメールは上記の通り必ずしもスパムとして扱われませんが、Spamhausは米国のCAN-SPAM法や欧州のGDPRなど、それぞれの国や地域の法律でB2Bメールに関するガイドラインが不完全であることから、このグレーゾーンがスパマー(スパム送信者)に悪用され、コールドメールの送信が行われていることが実情だと指摘しています。
日本では、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」が施行されており、同意を得ずに広告宣伝のために送信するメールは原則として禁止されています。
しかし、例外として以下の場合などでは、事前の同意なしに配信が可能とされています。
- 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合
- 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(広告拒否の文言がない場合)
もっとも、これらの例外に該当する場合であっても、Spamhausは次のような行為を「highly unethical(極めて非倫理的)」としています。
- ツールを使用して一斉配信を行う
- 受信者を欺くためのドメインの大量取得(gmail.comに対するgmai1.comなど、複数の類似ドメインによる分散配信による正規ドメインとの誤認やスパムフィルタの回避)
- エンゲージメントの偽装(開封やクリックの自演など、受信者の反応を装う行為)
つまり、法律上問題ない配信対象だからと言って、その配信が社会的に正しいか、受信者がそれを許容するかどうかは別問題ということです。
送信者に推奨される対策
結論として送信者は何をすればよいのかというと、受信者を欺くためのドメインの大量取得やエンゲージメントの偽装を行わないことは言わずもがな、スクレイピングやリスト購入によって入手したメールアドレスを登録せず、オプトインを得て正規の配信を行うこと、これにつきます。
また、Spamhausが「許可は譲渡できない」と述べている通り、オプトインを得たからと言って、他のサービスにまでオプトインが引き継がれるわけではありません。
一度オプトインを得たからと言って、そのメールアドレスに対して、全く異なる趣旨のメールを送信しないよう注意しましょう。
ワイメールで行える対策
ワイメールでは、代理登録(送信者がCSVやAPIなどで登録)/自主登録(受信者自身がフォームなどから登録)時にオプトインメールを送信し、読者自身がメール内の本登録リンクから登録することで初めて配信対象として反映される、オプトイン/ダブルオプトイン機能をご用意しています。
また、異なる趣旨の配信リストは別々のメールマガジンで管理することで、それぞれでオプトインの管理が可能です。
最後に
Spamhausは、プラットフォーム側にもコールドメールのような迷惑メールを容認しないこと、違反者に厳正な対応を行うことを推奨しています。
弊社では、迷惑メール報告窓口を設置し、迷惑メール受信の報告を受け付けているほか、クラウドベンダーと連携を取り、スパム報告やブラックリスト登録などの確認を実施しています。
各窓口を通じてワイメールのシステムから配信されたスパムメール(迷惑メール)の受信が報告された場合は、利用者への警告や事実確認を行い、警告後も改善が見られない場合や弊社の基準で悪質なスパマーと判断した場合には、サービスの強制停止を行うことで、サービス全体のレピュテーションを保つことに努めています。
また、Spamhausはコールドメールのベストプラクティスについて定義する取り組み「M3AAWG Position on Cold Email」に積極的に貢献しており、弊社でもこれに注目し、お客様に健全なメール配信環境をご提供できるよう努力していく所存です。
受信者との信頼関係を守ることこそ、長期的にメールマーケティングを成功させる唯一の方法かと思いますので、お客様におかれましても、今一度運用を見直し、健全なメールマーケティングにワイメールをご活用いただければ幸いです。
関連コラム